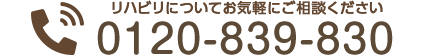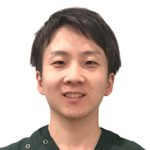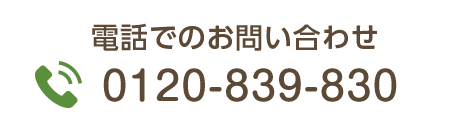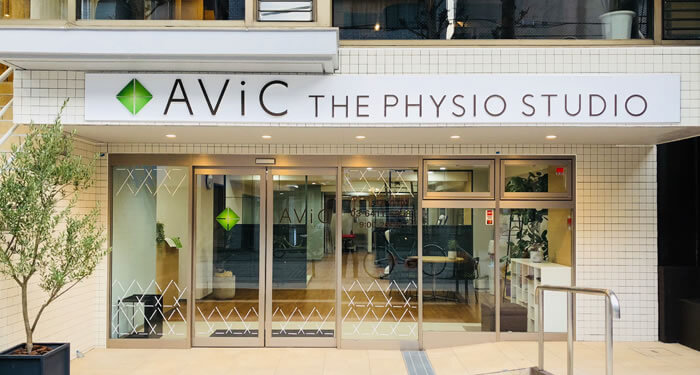脳梗塞後の手を自宅で改善!効果的な自主トレ6選

1日の生活を考えた時に、専門家とのリハビリは長くても3時間程度で、それ以外の時間の方が長いです。
その時間を効果的に使うことで、麻痺手の機能回復を促進できます。今回は、麻痺手に対するホームエクササイズの概要を紹介します。
1 ホームエクササイズの実施方法
以前紹介したリハビリ手法の記事はコチラ!「麻痺手の機能回復に重要な7つのリハビリ手法」
あなたが自宅でリハビリをする際にどのようなトレーニング内容がいいですか?どのような支援があると続けやすいと感じますか?
例えば『最先端のリハビリを自宅で受けたい』、『麻痺手をたくさん使い練習がしたい』、『道具を使って効率的にトレーニングしたい』、『トレーニング内容を詳しく教えて欲しい』、『自分にあった方法を教えて欲しい』、『ちゃんとできているか見て欲しい』など、ホームエクササイズに対する好みは多岐にわたると思います。
ここでは、エビデンスが示されているホームエクササイズの方法を紹介します。
1-1 麻痺手の機能トレーニング
病棟や自宅で、実生活での麻痺手の使用を想定した機能トレーニング(例:コップに向かって手を伸ばす、物品を握る・離す、タオルを畳む、物品をつまむ・離す など)です。[1–3]。あなたにあった課題内容と難易度を設定することが重要です。
1-2ミラーセラピー
手作りのミラーボックスあるいは市販の鏡を用いて実施します。麻痺手を鏡の後におき、鏡に映った麻痺していない側の手を見ながら練習します。あたかも鏡に映った手が、麻痺手のように錯覚することで、脳の機能回復を促す麻痺手の機能改善を促進する方法です。[4]。麻痺手の機能が低い方でも実施できます。
1-3 インタラクティブゲーム
脳卒中後の運動機能の改善には、強度の高い運度をたくさん反復することが重要とされています[5]。単純な反復練習は、継続するのに努力が必要です。そこで、ゲーム性のある機器を用いて、楽しく飽きずにトレーニングできる方法が用いられることもあります。例えば、Wii Sports[6]や仮想現実(VR)[7]が使用されています。VRとは、仮想空間内に麻痺手を生活場面で使用している様子を再現することが期待できる技術です。比較的麻痺手の機能が良い方が対象です。
1-4 電気刺激療法
電気刺激を単独、もしくは機能トレーニングに併用する方法です。電気刺激を使用することで、脳の神経を興奮させて機能回復を促進させることが期待できます。電気刺激には、感覚神経だけを刺激する方法[8,9]や筋肉と神経の両方を刺激する方法[10]があります。自宅で使用する電気刺激装置として、DRIVE-HOME(株式会社デンケン https://www.dkn.co.jp/health-care/drive-home/)があります。使用方法によっては、火傷などの皮膚損傷が生じる危険性があるので、注意が必要です。
1-5 CI療法
対象者の麻痺手(麻痺がある側の手)を利用した目標を達成し、実生活における麻痺手の使用を改善させることを目的としたプログラムです[11]。この手法を、自宅に専門家が訪問しての指導と介助者によるトレーニング補助を得ながら実施するトレーニングです。これにより、実生活での麻痺手の使用や動きの質の改善を認めています。[12]
1-6 ロボット療法
リハビリを支援する目的に開発されたロボットを使用し、麻痺手の機能回復を図るトレーニングです[13,14]。ロボットの種類は多岐に渡りますので、あなたにあったロボットを専門家の評価に基づき使用することと、使用方法を遵守することが重要です。また、ロボットは高価な機器になるため、ホームエクササイズとして使用している病院や施設は限られていると思います。
2 ホームエクササイズ実施方法によって効果は変わってしまうの?
エビデンスの示されている様々な種類のホームエクササイズがあるのは分かったが、実施方法によって効果が変わってしまうのではないかと不安がある方もいらっしゃるのではないかと思います。
ただ結論として、ホームエクササイズの実施方法により、効果に差がでるかどうか検証すると、実施方法によって差があるとは言えないという結果になります[16]。
また、トレーニング方法の提示も、一般的な紙面による提示方法と、スマートテクノロジー(動画や自動リマインダー機能)による提示方法を比較しても、トレーニングの実施頻度や効果に差があるとは言えないという結果です[3]。
つまり、ホームエクササイズはあなたが継続して実施できる方法を取り入れることが重要です。
当施設では、リハサクを用いた自主トレ支援や、自宅にいながらタブレットやPCで当施設のスタッフと繋がり、トレーニングを実施できる遠隔リハビリを提供しています。
自主練習を続けやすい工夫もされているので、継続するのに自信がない方もご活用いただきやすいご提案ができます。
出典
1. Brkic L, Shaw L, van Wijck F, Francis R, Price C, Forster A, et al. Repetitive arm functional tasks after stroke (RAFTAS): a pilot randomised controlled trial. Pilot Feasibility Stud. 2016;2: 50.
2. Harris JE, Eng JJ, Miller WC, Dawson AS. A self-administered Graded Repetitive Arm Supplementary Program (GRASP) improves arm function during inpatient stroke rehabilitation: a multi-site randomized controlled trial. Stroke. 2009;40: 2123–2128.
3. Emmerson KB, Harding KE, Taylor NF. Home exercise programmes supported by video and automated reminders compared with standard paper-based home exercise programmes in patients with stroke: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2017;31: 1068–1077.
4. Michielsen ME, Selles RW, van der Geest JN, Eckhardt M, Yavuzer G, Stam HJ, et al. Motor recovery and cortical reorganization after mirror therapy in chronic stroke patients: a phase II randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair. 2011;25: 223–233.
5. Langhorne P, Coupar F, Pollock A. Motor recovery after stroke: a systematic review. Lancet Neurol. 2009;8: 741–754.
6. Adie K, Schofield C, Berrow M, Wingham J, Humfryes J, Pritchard C, et al. Does the use of Nintendo Wii SportsTM improve arm function? Trial of WiiTM in Stroke: a randomized controlled trial and economics analysis. Clin Rehabil. 2017;31: 173–185.
7. Standen PJ, Threapleton K, Richardson A, Connell L, Brown DJ, Battersby S, et al. A low cost virtual reality system for home based rehabilitation of the arm following stroke: a randomised controlled feasibility trial. Clin Rehabil. 2017;31: 340–350.
8. Dos Santos-Fontes RL, Ferreiro de Andrade KN, Sterr A, Conforto AB. Home-based nerve stimulation to enhance effects of motor training in patients in the chronic phase after stroke: a proof-of-principle study. Neurorehabil Neural Repair. 2013;27: 483–490.
9. Sullivan JE, Hurley D, Hedman LD. Afferent stimulation provided by glove electrode during task-specific arm exercise following stroke. Clin Rehabil. 2012;26: 1010–1020.
10. Kimberley TJ, Lewis SM, Auerbach EJ, Dorsey LL, Lojovich JM, Carey JR. Electrical stimulation driving functional improvements and cortical changes in subjects with stroke. Exp Brain Res. 2004;154: 450–460.
11. Morris DM, Taub E, Mark VW. Constraint-induced movement therapy: characterizing the intervention protocol. Eura Medicophys. 2006;42: 257–268.
12. Barzel A, Ketels G, Stark A, Tetzlaff B, Daubmann A, Wegscheider K, et al. Home-based constraint-induced movement therapy for patients with upper limb dysfunction after stroke (HOMECIMT): a cluster-randomised, controlled trial. Lancet Neurol. 2015;14: 893–902.
13. Vloothuis JD, Mulder M, Veerbeek JM, Konijnenbelt M, Visser-Meily JM, Ket JC, et al. Caregiver-mediated exercises for improving outcomes after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12: CD011058.
14. Everard G, Luc A, Doumas I, Ajana K, Stoquart G, Edwards MG, et al. Self-Rehabilitation for Post-Stroke Motor Function and Activity-A Systematic Review and Meta-Analysis. Neurorehabil Neural Repair. 2021;35: 1043–1058.
脳梗塞のリハビリTips
AViC Report よく読まれている記事